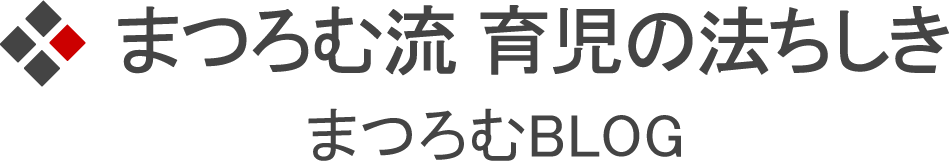出生後休業支援給付金の「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが確認できる書類
「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが確認できる書類
被保険者の配偶者が子を出産している場合(被保険者が父親、かつ、子が養子でない場合)は、被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」のいずれかに該当することから、母子健康手帳(出生届出済証明のページ)または医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)(いずれも写し可)を提出すれば、下表に記載の確認書類を省略することができます。
ただし、支給申請書の「配偶者の状態」欄には下表の該当する番号を記載します。
子の出生日の翌日における配偶者の状態
配偶者がいない 番号「1」
① 戸籍謄(抄)本(抄本の場合は被保険者本人のもの)及び世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し
または
②被保険者がひとり親を対象とした公的な制度を利用していることが確認できる書類(遺族基礎年金の国民年金証書、児童扶養手当の受給を証明する書類、母子家庭の母等に対する手当や助成制度等を受給していることが確認できる書類など、いずれか一つで可)
配偶者が行方不明(配偶者が雇用される労働者であり勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合又は災害により行方不明と
なっている場合に限ります。) 番号「1」
① 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
及び
② 配偶者の勤務先において無断欠勤が3か月以上続いていることについて配偶者の事業主が証明したもの、または、罹災証明書
配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない 番号「2」
戸籍謄(抄)本(抄本の場合は被保険者本人及び対象の子のもの。
住民票において、被保険者の配偶者が世帯主となっており、対象の子との続柄が「夫の子」又は「妻の子」となっている場合は、住民票(続柄あり)の写しでも可。)
配偶者から暴力を受け、別居中 番号「3」
裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10 条に基づく保護命令に係る書類の 写し、女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)のいずれか
配偶者が無業者 番号「4」
① 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
及び
② 配偶者の直近の課税証明書(収入なしであることの確認のため)
課税証明書に給与収入金額が記載されている場合は、事業主発行の退職証明書の写しなど子の出生日の翌日時点で退職していることがわかる書類も必要です。
配偶者が基本手当を受給中であれば、配偶者の直近の課税証明書に代えて受給資格者証の写しを添付書類とすることができます。
配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない 番号「5」
① 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
及び
② 配偶者の直近の課税証明書(所得の内訳の事業所得に金額が計上されており、給与収入金額が計上されていないことを確認するため)
課税証明書に給与収入金額が記載されている場合は、給与収入金額が雇用される労働者としてのものであれば、事業主発行の退職証明書の写しなど子の出生日の翌日時点で退職していることがわかる書類も必要です。
給与収入金額が労働者性のない役員の役員報酬である場合や、各種法律に基づく育児休業がない特別職の公務員の場合は、その身分を証明する書類(役員名簿の写しや、身分証の写しなど。)も必要です。
配偶者が産後休業中 番号「6」
母子健康手帳(出生届済証明のページ)、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書))、出産育児一時金等の支給決定通知書のいずれか
上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない 番号「7」
① 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
及び
② 配偶者が育児休業をすることができないことの申告書及び申告書に記載された必要書類。
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
日々雇用される者であるため
出生時育児休業の申出をすることができない有期雇用労働者であるため
労使協定に基づき事業主から育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたため
公務員であって育児休業の請求に対して任命権者から育児休業が承認されなかったため
雇用保険特例被保険者ではないため、育児休業給付を受給することができない
短期間用特例被保険者であるため、育児休業給付を受給することができない
雇用保険被保険者であった期間が1年未満のため、育児休業給付を受給することができない
雇用保険被保険者であった期間は1年以上あるが、賃金支払いの基礎となる日数や労働時間が不足するため、育児休業給付を受給することができない
配偶者の勤務先の出生時育児休業又は育児休業が有給の休業であるため、育児休業給付が受給することができない
(有給でなければ出生時育児休業給付または育児休業給付金が支給される休業を、期間内に通算して14日以上取得している必要があります)
出生後休業支援給付金とはに戻る
厚生労働省の育MENプロジェクトのバナーです。
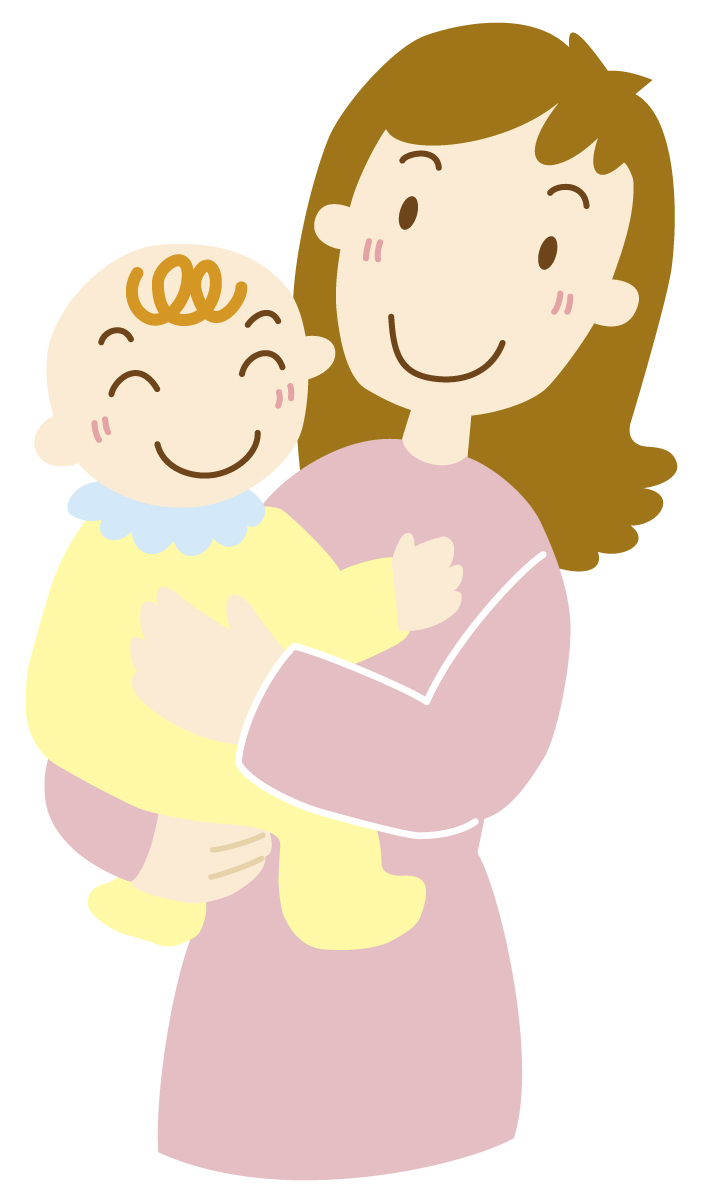
目次
産前産後休業・育児休業の豆知識
1 妊娠中の知識
妊娠したら会社に報告
妊娠中の業務の軽減
残業の免除
妊産婦検診に行くとき
妊娠中の医師等からの指導
母性健康管理指導事項連絡カードの使い方
2 産前産後休業の知識
産前休業はいつから取れるか
産前休業と有給休暇
育児時間について
3 産前産後の給付・保険料免除
出産手当金について
出産育児一時金
出産費用の直接支払制度
産前産後の社会保険料の免除
健康保険の扶養に入れる
産休復帰後の社会保険料の見直し
4 育児休業の知識
育児休業について
出生時育児休業について
育児休業はいつまで取れるか
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業の対象者
育児休業取得の申請について
育児休業の延長(1歳時点)
育児休業の延長(1歳6か月時点)
育児休業中の就労について
5 育児休業中の給付・保険料免除
育児休業給付
出生後休業支援給付金(2005年4月1日より)
育児休業中の社会保険料の免除
育児休業復帰後の社会保険料の見直し
育児休業中に退職するとどうなるか
育児休業中の社会保険r表免除はいつまでか
6 仕事と育児の両立のための制度
仕事と育児の両立支援制度には何があるか
育児短時間制度とは
短時間勤務の給与
育児短時間就業給付金(2025年4月1日より)
3歳から小学校入学前までの柔軟な制度
看護休暇
子供の行事参加のための休暇制度
残業免除の制度
時間外労働の制限とは
深夜業の制限とは
7 仕事と育児の両立制度の給付金
育児時短就業給付金(2025年4月1日より)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類の見直し
子育て中に転職するとき