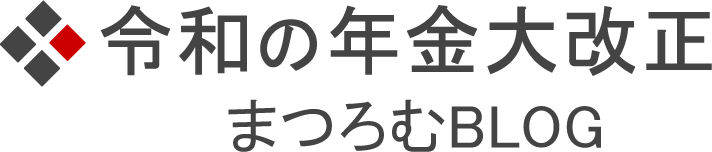年金の繰下げ受給
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、65歳で受け取らずに66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。
繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。

また、特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達したときは速やかに請求してください。
請求の時効は5年ですので、お気を付けください。
昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
繰下げ加算額
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
ただし、65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。
増額率 (最大84%) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
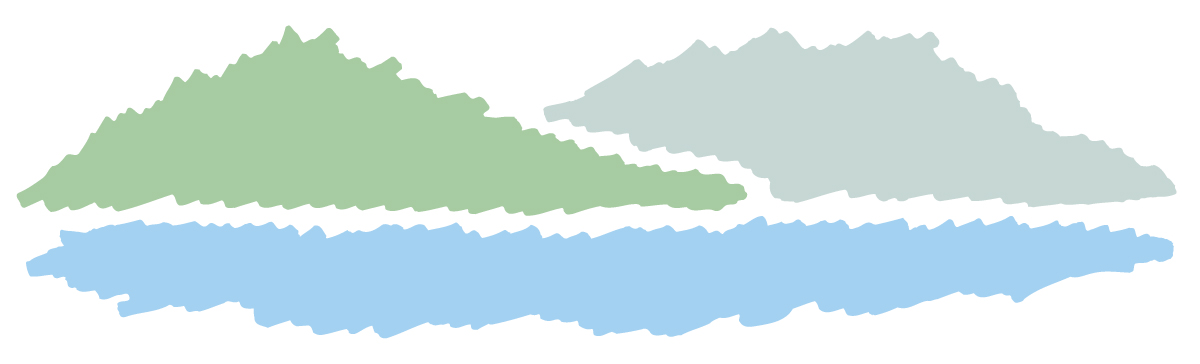
1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
3 65歳以降に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算します。
繰下げの注意点
繰下げをする際は、以下の点にご注意ください。
①加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。
また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。

つまり繰下げ待機期間中の加給年金額や振替加算は、一切もらえなくなります。
加給年金額は、年額388,900円(令和4年度)ですので、3年繰下げるとすると「1,166,700円」は諦めることになります。
ご主人と奥様の年齢差が大きければ大きいほど、加給年金額は長くもらえますので、繰下げするかどうか検討をする必要があります。
ただし、老齢厚生年金を繰下げた場合もらえなくなりますが、老齢基礎年金のみ繰下げた場合は加給年金額はもらえます。
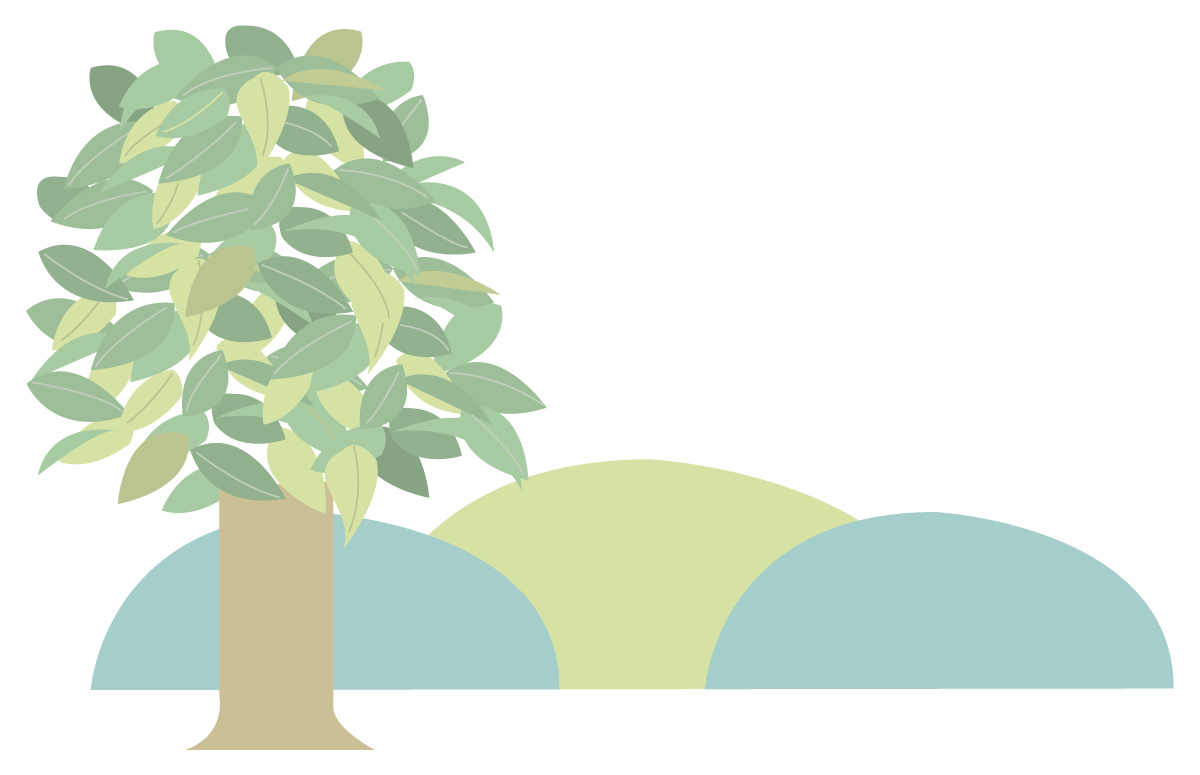
②65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。
増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され支払われます。
③昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。
④日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけません。
⑤65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。
ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができます。
⑥66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。
このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。
⑦厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、年金の支払元である基金等にご確認ください。
⑧このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。

⑨繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません。
繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われます。
ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。
⑩繰下げ請求により増額された年金を受給することのほか、過去時点の年金額で過去分の年金を一括して受給することもできます
繰下げ請求により増額された年金を受給することのほか、以下の①・②のとおり、過去時点の年金額で過去分の年金を一括して受給することもできます。
なお、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金、受給した年金生活者支援給付金や傷病手当金に影響がある場合があります。
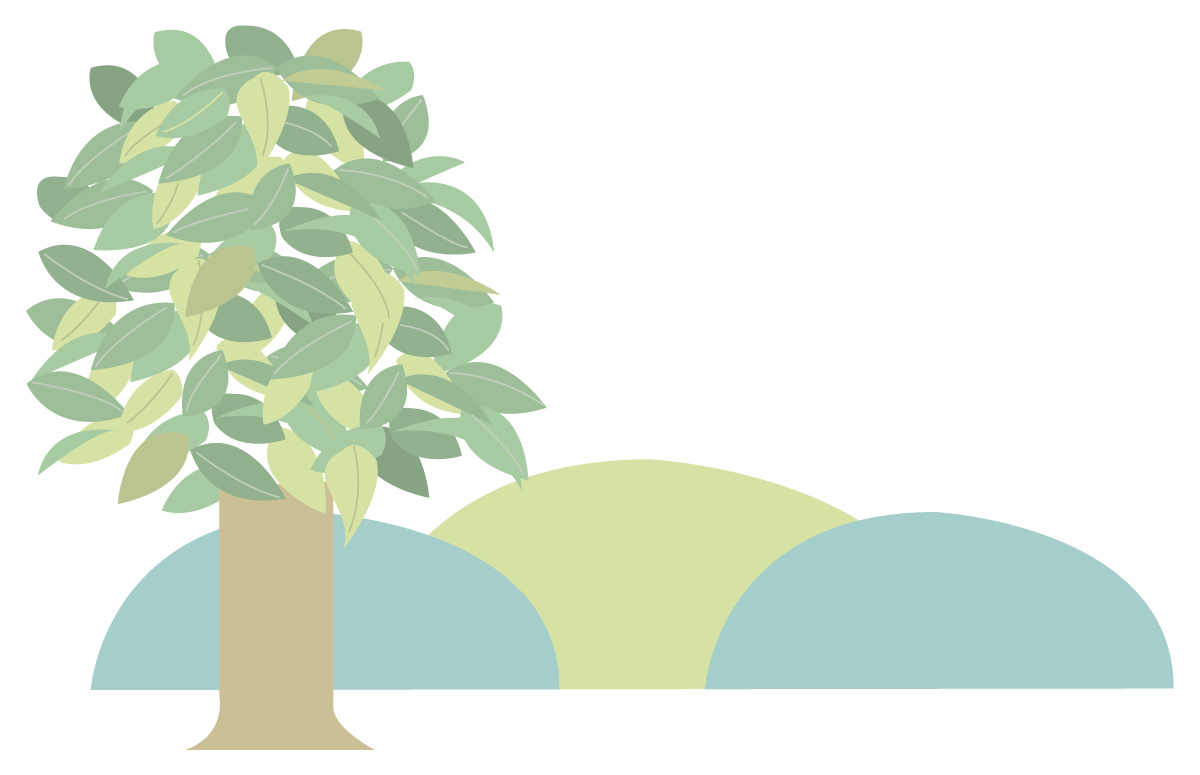
①生年月日が昭和27年4月1日以前の方
65歳時点の年金額で過去分の年金を一括して受給することができます。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は、時効により受け取れなくなります。
②生年月日が昭和27年4月2日以降の方
70 歳到達までは 65 歳時点の年金額で、70 歳到達後は請求の5年前時点の増額された年金額で、過去分の年金を一括して受給することができます。
ただし、請求した時点から5年以上前の年金は、時効により受け取れなくなります。
(なお、令和5年3月までに請求した場合は、70 歳到達後も、請求の5年前時点の増額された年金額での支給は行われず、65歳時点の年金額での支給が行われます。)
繰下げ受給のデメリット
繰下げ受給のデメリットは、いくつかあります。

その一つが、繰下げ待期を終えて、年金を請求してすぐに亡くなった場合です。
例えば、70歳まで繰下げをして、受給を開始して2か月で病気で亡くなったとします。
その場合は、繰下げした増額率で年金をもらえるのですが、死亡した時までとなり2か月分の年金しかもらえません。
65歳から受給を開始しておれば、5年と2か月分もらえたのですが、その差はあまりにも大きいです。
繰下げ待期中に亡くなった場合は、最大5年分(65歳から亡くなった時点までの分ですが)未支給年金として奥さんがもらえます。
しかし、繰下げ待期を終えて、請求をしだしてから亡くなるとそれができなくなります。
寿命は、誰にも分かりませんので、繰下げ受給をするかどうかは自分で判断するしかありません。
基金加入者の方へ
厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受給している方が、老齢厚生年金の支給の繰下げ請求を希望する場合は、基金等の年金も合わせて繰下げとなりますので、年金の支給先である基金等にご連絡をお願いします。
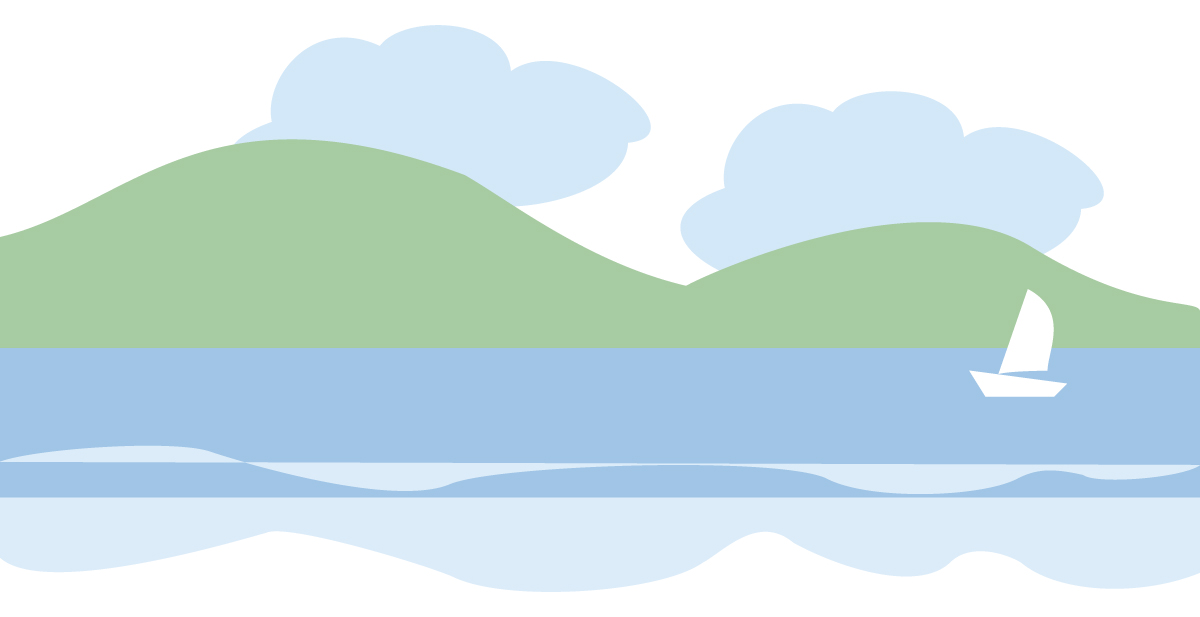
在職老齢年金制度により支給停止される額
65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合は支給停止されていた額を除いて繰下げ加算額を計算します。

具体的には、繰下げ加算額に平均支給率を乗じることにより計算します。
平均支給率=月単位での支給率の合計÷繰下げ待機期間
月単位での支給率=1-(在職支給停止額÷65歳時の老齢厚生(退職共済)年金額)
老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ
老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせが日本年金機構から届きます。
①66歳から74歳までの方
年金制度の改正により、令和4年4月から繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられることに伴い、66歳以降に繰下げ受給を希望され、老齢年金を受給されていない方に対し、ご希望する時期に適切に繰下げ受給できるよう、66歳から74歳までの間、毎年「年金見込額のお知らせ」が送付されます。

②75歳に到達された方
また、老齢年金を受給されていない方で、75歳に到達される方には、75歳の誕生日の属する月の前月に年金請求書を送付されます。

66歳から74歳の方へのお知らせ
1.対象となる方
昭和27年4月2日以降生まれの方で、次の条件に当てはまる方
老齢年金を受給していない方(特別支給の老齢厚生年金を受給していても対象となります)
老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給していない方
※遺族年金または障害年金を受給している場合や共済組合の加入期間がある場合等は送付対象外です。

2.送付時期
66歳から74歳まで、毎年、誕生日の前日の属する月の前月末頃に送付します。

3.お知らせの内容
繰下げ見込額等を記載した「年金見込額のお知らせ」を送付します。
(1)老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給されていない方(双方を受給されていない方も含む)
(2)特別支給の老齢厚生年金を受給されていない方
75歳に到達する方へのお知らせ(年金請求のご案内)
1.対象となる方
75歳の誕生日を迎える方で、次の条件に当てはまる方
老齢年金を受給していない(特別支給の老齢厚生年金を受給していても対象となります)
老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給していない
遺族年金または障害年金を受給している場合や共済組合の加入期間がある場合等は送付対象外です。

2.送付時期
75歳の誕生日が属する月の前月に送付します。
お知らせの内容
年金を受け取るために必要な年金請求書等を送付します。
目次
当サイトはリンクフリーです。管理人の許可なく自由にリンクを張って頂いて問題ございません。