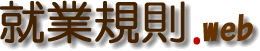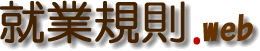|
☆無料診断お問い合わせ
☆ひながた(テンプレート)
1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項
2.就業規則の作成
2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務
3.労働時間制
3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制
4.賃金規程
4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与
5.育児介護休業 他
5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度
★改正男女雇用機会均等法
(平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
★.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新
6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他
7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律
8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務
9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策
10.その他の関連情報
10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
▼定年延長・雇用継続Q&A
▼労働審判法 |
9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
5.高齢者の経験を生かす職域の確保
高齢者一人ひとりが定年齢到達年前に就いていた仕事、蓄積した能力に応じて就業可能性が異なっていますので、高齢者雇用を促進するにあたっては、このような違いを踏まえて検討することが必要です。
基本的には、高齢者の保有する能力を十分に活用して即戦力の労働者として働くことができるように、定年年齢到達後についても現職を継続して行うことになります。
一方、若年・中堅従業員が中心となって働いている職場の場合は、若年・中堅従業員をサポートしたり、高齢者の持つ高度なスキルを継承するような役割を持たせることで高齢者を活用していくことが考えられます。
高度成長に伴う事業拡大期に大量に入社し、現在企業の中核となっている団塊の世代が、今後大量に定年退職期を迎えることになります。
豊富な経験に培われた高いスキルを保有するベテラン社員の退職により、企業の競争力は大きな影響をこうむると考えられることから、こうしたベテラン社員の知識・技能・経験を早急に若手世代に継承することが求められています。
こうした状況下だからこそ、定年年齢を超えた高齢者を教育要員として活用する必要性が高まっています。
高齢者雇用の促進のためには、高齢者の保有する能力を十分に活用できるように、定年年齢以前に就いていた職能を継続して行うことが基本となりますが、それがかなわない場合には、配置転換も考えなくてはなりません。ただし、その場合であっても、100%異なった業務ではなく、定年年齢到達者の知識、技能、経験、資格等を生かすための配置転換が求められます。
高齢者に求められているのは、職業生活の過程で蓄積してきた豊かな経験や知識、ノウハウを活かして、企業に貢献することです。
したがって、従業員一人ひとりが日頃から業務に直接関係する資格の取得はもちろん、広く経営に役立つ資格の取得といった自らの職業能力の向上に主体的に取り組み、高齢期に至っても第一線で働くことができるような能力を身に着けていくことが前提条件となります。
加えて、高齢者としても60歳以降も第一線で働き続けようと思えば、世の中の変化に対応できるよう、パソコン等新しい機械・器具の操作に積極的にチャレンジするといった姿勢も重要です。
一方、こうした従業員個々人の自助努力を積極的に支援するため、企業としても、若年期から高齢期に至るまで段階的に能力開発を行うことが必要です。
|