障害年金請求の仕方
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.16
障害年金の請求は、請求する人またはご家族を社会保険労務士など専門家が援助しないと進まない面があります
その理由はいくつかあります。
あいまいな知識を持って年金事務所に行くと、年金事務所は相談記録を取っており、誤った情報などが記録さることがあります。
正確な情報を年金事務所にお話する必要があります。
そのため、社会保険労務士に事前に相談の乗ってもらうのが一番です。
援助が必要な理由としては、

①請求手続が複雑で理解しにくい、
②診断書を書く上で必要な現症年月日などの確認が難しい、
③裁定請求書の書き方がわからない、
④病歴・就労状況申立書の書き方がわからない、
⑤請求手続に時間がかかり精神的なエネルギーを要するなどをあげることができます.。
受給要件を確認
障害年金が複雑でわかりにくいのは、ある程度の医学的知識が必要であるということと、それが長期保険(保険料を長い期間掛ける保険)であるということからきています。

健康保険などの医療保険を短期保険といい、年金保険を長期保険といいますが、ここで長期保険というのは二つの意味をもっています。
一つは、保険が対象とする生活事故としての高齢・死亡・障害がいずれも長期に及ぶこと、もう一つは年金を受ける条件、つまり「受給要件」が長期間の加入要件(一定以上の保険料を納めていること)を要することです。
つまり、年金制度では給付の面でも受給要件の面でも時間=歴史のもつ要素が大変重要だということです。
障害年金を歴史との関係で整理すると、
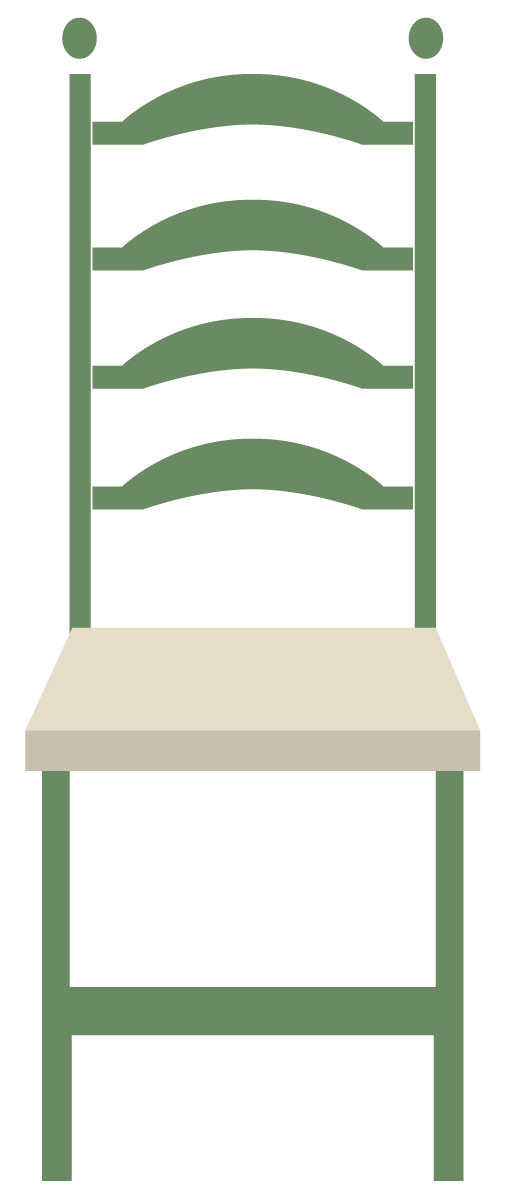
①年金制度の歴史
②個人の加入暦(職歴・保険料納付歴)
③病歴・障害暦の三つの軸を区別することができます。
これまでの年金制度の歴史では、加入対象が徐々に拡大し、保険料の納付要件も緩和され、障害対象の範囲も拡大されてきました。
こうした年金制度の歴史と、個人の歴史(加入暦と病歴)をつきあわせることが大切です。

年金制度の変遷過程のなかで、どの時期に発病があり、初診日がいつだったのか、その時は何歳であり、何の制度(国民年金なのか厚生年金等なのか)に加入しているかをきちんと確認することが、受給要件を確認したり、障害年金に該当するかどうかをみるうえで大変重要です。
まずは、障害年金の申請を専門に手掛けている社会保険労務士に相談するのが一番かと思います。
受給三要件
受給要件を満たすための三つの要件は、
①初診時に公的年金制度に加入していること、
②加入すべき期間について定められた条件の保険料を納付していること、
③障害を認定すべき日に所定の障害状態にあることの三つです。

基本はこの三要件のすべてを満たすことですが、国民年金では初診時の年齢によって必ずしも三つの要件をすべて満たさなくてもよい場合があります。
受給三要件は、障害年金の申請を専門に手掛けている社会保険労務士に相談するのが一番かと思います。
障害年金無料小冊子を作成しました。
申込みは、下記バナーをクリックしてください。
保険料納付要件
3分の2以上納付(原則)または直近1年間に未納がない(特例)の2つの納付要件のいずれかを満たしていることが必要となります。
あくまでも初診日の前日における納付状況に基づき要件判定がされます。
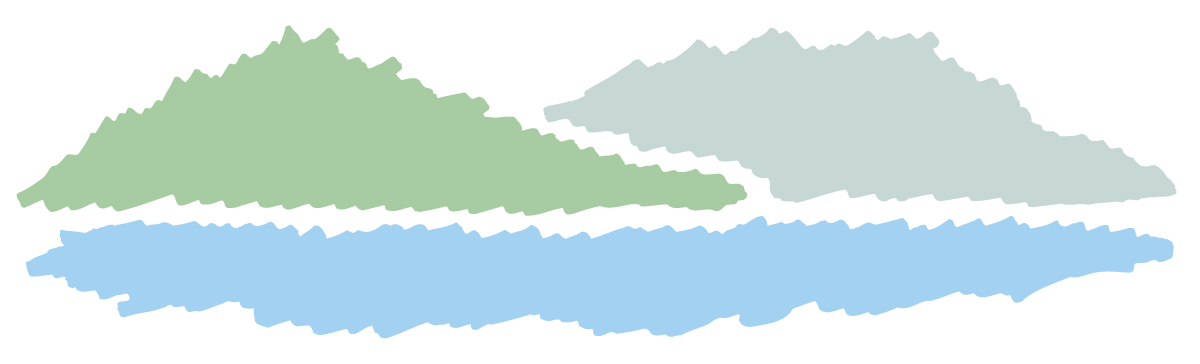
◎3分の2以上納付(原則)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、納付済か免除されているか否かを判定します。
納付しているとみなされるのは、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)の合計です。

◎直近1年間に未納がない(特例)
次のすべての要件を判定します。
・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない
・令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
年金事務所に行くと、保険料納付状況の資料を入手できます。
その納付記録を元に、保険料納付要件が満たされているかを確認します。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。







