労働者派遣に関する情報
労働者派遣に関する情報を掲載しています。
これから派遣で働こうとする方と派遣をする会社、派遣を受け入れる会社に役に立つ情報を提供しています。
派遣の為に役立つ知識、労働者派遣法の改正、業務取扱要領、派遣先の会社がしなければならない事項などを掲載する予定です。
どうぞご利用下さい。
リクナビ派遣(PR)

人材派遣ってなに
正社員やアルバイトですと、ふつうは雇われた会社イコール勤務先です。
でも派遣社員の場合は、雇われているのは派遣会社だけれど、実際に仕事をするのは別の会社になります。
雇用先と勤務先が分かれているのが、派遣という働き方の特徴です。
給与を支払うのは派遣元である派遣会社ですが、実際にやる仕事の内容や勤務時間は、派遣会社との間で結ぶ雇用契約によって決まります。

派遣のメリット・デメリット
派遣社員として働くメリットは、自分のライフスタイルやライフプランに合わせて働く時間や日数、職種、勤務地などを選べることです。
正社員に比べると残業が少ないため、小さな子さんを持つ方や親御さんの介護をする方にとっても働きやすいという点があります。
また、正社員よりも派遣社員の方が大企業で働くことができるチャンスがあるため、大企業で働いてスキルや知識を身につけ、正社員として転職する際に役立てるという道もあります。

デメリットは、契約期間に限りがあることです。
派遣契約は主に3か月ごとか6か月ごとになっており、契約期間が満了したときに契約を更新するかどうか派遣先会社が決定します。
あなたの能力が評価されなかったり、またあなたがどんなに仕事を頑張っていても派遣先会社側の事情(育休社員の復帰など)で派遣社員が必要なくなれば、契約は更新されません。
また、契約が更新され続けたとしても、最長で3年間という限りも設けられています。
一つの職場で長く働きたいという考えの方にとってはデメリットとなります。
反対に、色々な職場で経験を積みたいと考えている方にとってはデメリットではなくなります。
あなたがどのような考えをもち、どうやって仕事をしていきたいかを考えたうえで、派遣社員として働くかどうかを決めていきましょう。
派遣の時給の相場
派遣社員の給与は、派遣先会社が派遣元会社に支払った「派遣料金」から、社会保険や、派遣会社運営のための必要経費(いわゆるマージン)が引かれたものとなります。
マージンの割合は派遣元会社によって異なるため、派遣会社を選ぶときの一つの参考にするといいでしょう。

一般的に、専門的な知識や技術が必要となる職種は時給が高い傾向にあります。
また、同じ職種なら、スキルが高い人ほど当然時給は高くなります。
派遣社員は契約期間に限りがあるという不安定さや、専門的な仕事を任せられる即戦力としての価値があることから、中には正社員として働くよりも高い給与が見込める場合もあります。
ただし、基本的にはボーナスは支払われません。
派遣のQ&A
派遣で初めて働きますが、契約書にある労使協定対象とは何ですか?
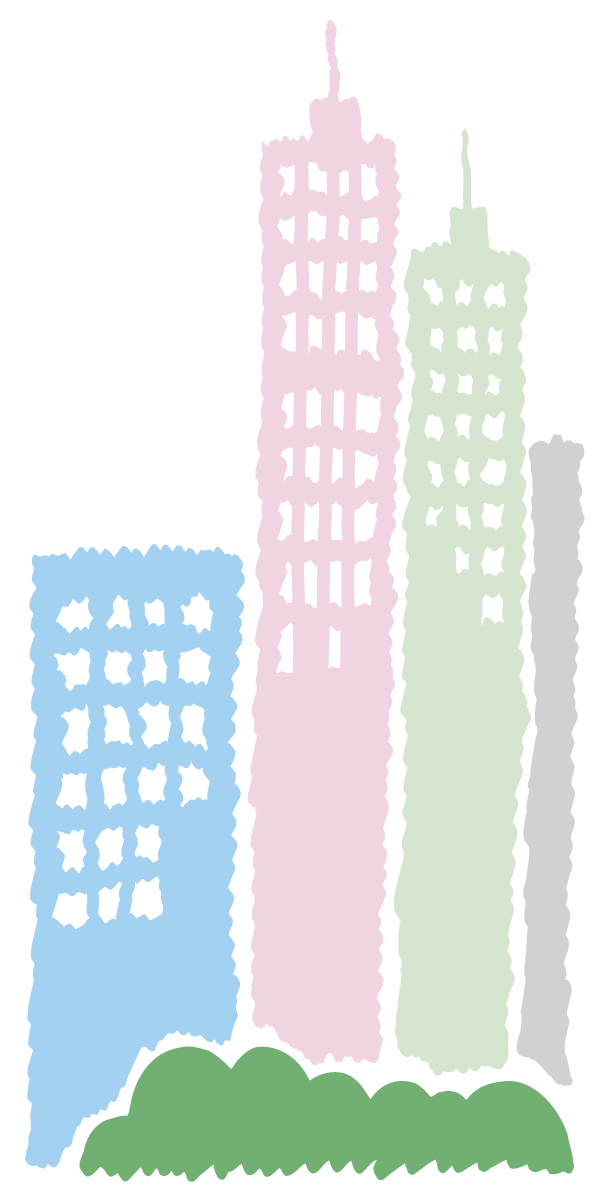

目次
当サイトはリンクフリーです。管理人の許可なく自由にリンクを張って頂いて問題ございません。
